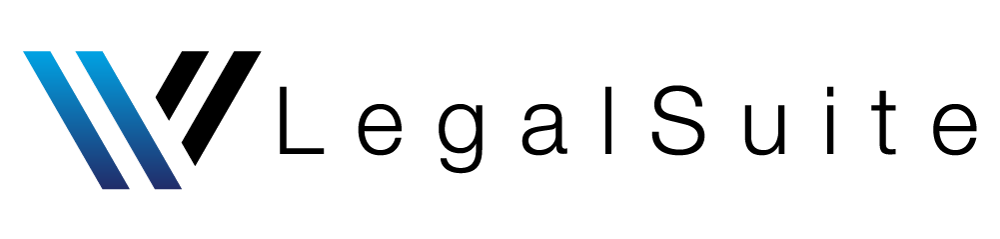【予備試験】平成31年刑法【答案例と解答のポイント】

出題の趣旨
本問は,甲が,(1)Vから本件土地に対する抵当権設定の代理権しか付与されていなかったのに,Aに本件土地を売る旨の売買契約書2部に「V代理人甲」と署名した上,その内容をAに確認させるなどしたこと,(2)Vに無断で本件土地の売買契約をAと締結したこと,(3)(2)に関して,逮捕を免れるなどのために,Vを殺害してその死体を海中に捨てることを計画し,実際にVの首を絞めたが,それにより失神したVが死亡したものと軽信し,その状態のVを海に落とし溺死させたことを内容とする事例について,甲の罪責に関する論述を求めるものである。
https://www.moj.go.jp/content/001309069.pdf
(1)については,本件土地の売買契約書の作成権限が与えられていなかった甲による同契約書の作成が代理権限の逸脱に当たることを前提に,有印私文書偽造罪・ 同行使罪の成否について,文書の名義人に関する擬律判断を含め,その構成要件該当性を検討する必要がある。
また,(2)については,主に論ずべき点として,横領罪と背任罪の関係を踏まえて,本件土地に関する(横領罪における)占有が甲に認められるか,それが認められるとした場合に甲の行為が「横領」と評価できるか(既遂時期),仮に横領罪の成立が否定された場合に背任罪の成否を検討すべきかについて,本事例における事実関係を基に検討する必要がある。
(3)については,行為者が第1行為(Vの首を絞める行為)により死亡結果が発生すると予見していたのに,実際は結果が発生せず,第2行為(失神したVを海に落とした行為)により死亡結果が発生した場合(いわゆる遅すぎた構成要件の実現)の殺人既遂罪の成否に関し,第1行為と死亡結果との因果関係の有無及び因果関係の錯誤の処理,並びに,第2行為の擬律(抽象的事実の錯誤,過失致死罪の成否)について,また,第1行為と第2行為を1個の行為(一連の実行行為)と捉えた場合は,1個の行為と評価する根拠について,それぞれ検討する必要がある。
いずれについても,各構成要件等の正確な知識,基本的理解や,本事例にある事実を丁寧に拾って的確に分析した上,当てはめを行う能力が求められる。
答案例
第1 本件土地をAに売却した行為について
横領も背任も成立し得る法条競合の関係に立つため、重い横領から検討する。
1 業務上横領罪(刑法(以下略)253条)の検討
⑴ア 本件土地はVの所有物であるから「他人の物」にあたる。
イ 「自己の占有する」とは濫用のおそれのある法律的支配も含み、自由に処分し得る状態であれば認められると考える。本件で甲は本件土地の登記済証や委任事項欄の記載がない白紙委任状等を預かっているから、自由に処分し得る状態といえ、「自己の占有する」にあたる。
ウ 「業務上」とは社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務のうち、他人の財産を管理するものをいうと考える。本件で甲は不動産業者という社会生活上の地位に基づき反復継続して、本件土地を管理しているから「業務上」にあたる。
よって「業務上自己の占有する他人の物」にあたる。
⑵ 「横領」とは、委託の任務に背いた権限逸脱行為であり不法領得の意思を発現する行為をいい、不法領得の意思とは所有者でなければできないような処分をする意思をいうと考える。本件で甲はVから抵当権の設定権限を付与されたにすぎないのに売却しているから、委託の任務に背いた権限逸脱行為に当たる。また、甲は借金返済のために売却しているから、所有者でなければできないような処分をする意思を発現している。よって「横領」行為は認められる。
⑶ 「横領した」といえるためには、所有権侵害が必要であると考える。本件で所有権をAに移転するのは某月16日とされていたのであるから、同月6日時点では所有権は移転しておらず所有権侵害はない。よって「横領した」にはあたらない。
以上から、業務上横領罪(253条)は成立しない。
2 背任未遂罪(250条、247条)の検討
⑴ 甲は「他人」V「のために」抵当権設定をする者であるから、「その事務を処理する者」にあたる。
⑵ 「任務に背く行為」とは、両当事者間の合意に反し、かつ、財産的損害の危険性ある行為をいうと考える。本件で甲はVとの合意に反し売却に及び、かつ、Vは本件土地を失うという財産的損害の危険性があるから、「任務に背く行為」にあたる。
⑶ もっとも本件では表見代理の適用はないから、Vに「財産上の損害を加えた」とはいえない。
⑷ 「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」(図利加害目的)とは、本人の利益を図る目的がなく自己又は第三者の利益を図る認識があることをいうと考える。本件で甲は自己の借金返済に充てるつもりだったから、本人Vの利益を図る目的がなく、自己の利益を図る認識がある。よって図利加害目的がある。
⑸ 甲はこれらを認識・認容しているから故意(38条1項本文)がある。
以上から、①背任未遂罪(250条、247条)が成立する。
第2 売買契約書を作成・交付した行為について
1 無印私文書偽造罪(159条3項)の検討
⑴ 「権利、義務…に関する文書」とは権利義務を発生させる文書をいうと考える。本件売買契約書により所有権という権利移転が発生するから「権利、義務…に関する文書」にあたる。
⑵ 「偽造」とは、名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいい、名義人とは文書上作成者として認識される者を、作成者とは意思観念の表示主体をいうと考える。本件売買契約書では「V代理人甲」との記載により本人Vに効果帰属すると文書上認識されるため名義人はVである。一方、本件売買契約書は甲が勝手に作成したものであるから甲の意思観念が表示されているといえ、作成者は甲である。よって名義人と作者の人格の同一性を偽っており、「偽造」にあたる。
⑶ 有印とは名義人の署名・押印があることをいうと考える。本件で名義人Vの署名・押印はないから、無印である。
⑷ 「行使」とは偽造文書を真正文書として使用することをいい、使用とは当該文書を認識させることをいうと考える。本件で甲は本件売買契約書を真正文書としてAに認識させるつもりであるから、「行使の目的」がある。
⑸ 甲は、これらを認識・認容しているから故意がある。
以上から、②無印私文書偽造罪(159条3項)が成立する。
2 偽造無印私文書行使罪(161条1項)の検討
⑴ 甲は本件売買契約書を真正文書として交付してAに認識させたといえ「行使」にあたる。
⑵ 甲は、これらを認識認容しているから故意がある。
以上から、③偽造無印私文書行使罪(161条1項)が成立する。
第3 Vを殺害した行為について
1 殺人罪(199条)の検討
⑴ 「殺」すとは死の結果発生の危険性ある行為をいうと考える。本件で、甲はVの首を背後から力いっぱいロープで絞めているから死の結果発生の危険性ある行為をしており、「殺」すにあたる。そして、Vの死亡という結果が発生している。
⑵ もっともVの死因は溺死であるから因果関係があるか。因果関係は条件関係が認められることを前提に、行為の持つ危険が結果へと現実化したといえることが必要であると考える。本件で、甲の絞首行為がなければVは死亡しなかったから条件関係はある。そして死因が溺死である以上介在事情の寄与度は大きい。もっとも、溺死は証拠隠滅のために行われたのであるから、絞首行為に誘発されている。しかも証拠隠滅のために溺死させることはままあるから異常性は低い。よって、行為の持つ危険が結果へと現実化したといえるから、因果関係がある。
⑶ 甲は絞首行為の危険性を認識しているし、免許取り消しを免れるという動機もあるので、認容もある。よって故意が認められる。
⑷ そして溺死という因果経過は認識していないが窒息死という因果経過を認識している以上、反対動機の形成は可能であるから故意は阻却されない。
以上から④殺人罪(199条)が成立する。
2 過失致死罪(210条)の検討
⑴ 甲は生きているVを海へ投げて殺しているから、客観的には殺人罪を実現しているが主観的には死体遺棄罪(190条)の故意しかないから、抽象的事実の錯誤の問題となる。 「重い罪」で「処断…できない」(38条2項)とは、責任主義の観点から重い罪は成立しないという意味であると考える。よって殺人罪は成立しない。
⑵ 本件では軽い罪の死体遺棄罪の故意はあるから、殺人罪の構成要件の中に死体遺棄罪の構成要件が含まれているか問題となる。その際には、保護法益に共通性があるか否かにより判断する。本件で、殺人罪の保護法益は人の生命である一方、死体遺棄罪のそれは死者に対する宗教的感情であるから共通性がない。よって、殺人罪の構成要件の中に死体遺棄罪の構成要件が含まれていない。以上から故意犯は成立しない。
⑶ もっとも、より注意をすればVが生きていたことに気付けたので甲に過失が認められ、⑤過失致死罪(210条)が成立する。
第4 罪数
死の二重評価を避けるため⑤は④に吸収される。②と③は通例手段と結果の関係にあるから牽連犯(54条1項後段)となり、それと①④は併合罪(45条前段)となる。
以上
解答のポイント
業務上横領罪(253条)
- 第一次的な保護法益は所有権、第二次的な保護法益は委託信任関係です。
- 成立要件は、以下の通りです。
- 業務上自己の占有する他人の物を(客体)
- 横領(実行行為)
- した(結果)
- 客体のポイント
- 当てはめでは、まず「他人の物」にあたること簡単に認定しましょう(そもそも自己物は横領罪の対象ではないため)。その後に、その物を「自己が占有」しているといえるか、さらにそれが「業務上」と言えるかを認定すると奇麗な当てはめになります。
- 「自己が占有」しているかの当てはめ
- 物理的に物を直接握持しているケースでは、「自己が占有」しているのは当然ですから、問題文の事実を拾って簡潔に認定してください。
- 物理的に物を直接握持していないケース(代表例は、不動産や預金が挙げられます)では、「自己が占有」しているかが問題になります。したがって、「自己が占有」していると言えるためには法律上の支配も含む旨の論証が必要です。
- 「業務上」の当てはめ
- 「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務のうち、委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とする事務をいうという定義は暗記しましょう。
- なお、単純横領罪(252条1項)においては、書かれざる構成要件要素として委託信任関係が求められますが、業務上横領罪(253条)においては不要です。なぜなら、上記「業務」の定義中に”委託を受けて”が既に含まれているため、「業務」の認定を行えば、委託信任関係の認定も自ずとなされるので、単独の成立要件として認定する必要はないからです。
- 実行行為のポイント
- 「横領」とは、委託の任務に背いた権限逸脱行為であり、不法領得の意思を発現する行為をいい、不法領得の意思とは所有者でなければできないような処分をする意思をいうという定義は暗記しましょう。
- 上記定義中の”不法領得の意思の発現行為”が、第一次的な保護法益である所有権に対応しています。
- “委託の任務に背いた権限逸脱行為”が、第二次的な保護法益である委託信任関係に対応しています。
- 上記2点を当てはめた後の結論部分では、「横領した」とは書かないでください。このように書くと、結果の概念を含んだ記述になってしまいます。”「横領」行為にあたる”などの記載に留めましょう。
- 「横領」とは、委託の任務に背いた権限逸脱行為であり、不法領得の意思を発現する行為をいい、不法領得の意思とは所有者でなければできないような処分をする意思をいうという定義は暗記しましょう。
- 結果のポイント
- 結果は法益侵害が発生したことを言いますから、保護法益が害されたことが必要です。殊、横領罪においては第一次的な保護法益は所有権ですから、所有権が侵害されたことを示して初めて「横領した」と言えることになります。
私文書偽造罪(159条)
- 保護法益は文書に対する公共の信用です。
- 成立要件は、以下の通りです。
- 「権利、義務…に関する文書」もしくは「事実証明に関する文書」を(客体)
- 「偽造」し(実行行為)
- 「他人の印章若しくは署名を使用して」「偽造した他人の印章若しくは署名を使用して」(有印性)
- 「行使の目的で」(条文上の目的)
- 客体のポイント
- 「権利、義務…に関する文書」とは権利・義務の発生・変更・消滅に関する文書をいい、「事実証明に関する文書」とは実社会に交渉を有する事項を証明するに足りる文書を言います。定義として示せるように暗記し、どちらの文書に該当するのかを区別して論じましょう。
- 実行行為のポイント
- 「偽造」とは名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいい、名義人とは文書上作成者として認識される者を、作成者とは意思・観念の表示主体をいうまでセットで暗記しましょう。
- 当てはめにおいては、名義人は〇〇、作成者は△△ときちんと特定をしたうえで、人格の同一性を偽っていると結論付けしょう。
- 有印性のポイント
- 有印は、「他人の印章若しくは署名を使用」していれば認められます。すなわち、他人である名義人の印章若しくは署名が使用されていれば有印文書(1項)となります。一方、名義人の印章若しくは署名が使用されていなければ無印文書(3項)となります。
- 有印性は「偽造」(実行行為)の後に認定しましょう。有印とは上記の通り名義人の印章・署名があることですから、「偽造」の当てはめにおいて名義人を先に特定しておく必要があるからです。
- 条文上の目的のポイント
- 「行使の目的で」は主観面です。すなわち、客観面の検討をすべて終えた後に認定してください。もっとも、条文に明記された主観面ですから、故意よりは先に認定する必要があります。
- 「行使」とは、偽造文書を真正文書として使用することをいい、使用とは文書の内容を相手方に認識させ、又は認識可能な状態に置くことをいうという定義は暗記しましょう。
- なお、本罪以外にも、条文上の目的が規定されている犯罪があります。背任罪(247条)では「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」が、事後強盗罪(238条)では「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪責を隠滅するため」が規定されていますので、チェックしておきましょう。
刑法各論の問題は、紙面・時間が許す限り、定義を示したうえで、当てはめるようにしましょう。
遅すぎた構成要件の実現
第1行為で結果が生じたと誤信して、犯行隠蔽のために第2行為に及んだら第2行為で結果を実現してしまった場合、両行為は別々に検討する必要があります。なぜなら、第1行為は殺害目的で行われ、第2行為は死体隠蔽のために行われているので、意思の連続性がないため両行為を一体的に捉えることはできないからです。
- 第1行為について
- 第1行為について第1行為(実行行為)と溺死(結果)との間には、第2行為が介在しているため、因果関係が認められるかが問題となります。また主観的にも溺死するとは思っていないため、因果関係の錯誤も問題になります。
- 因果関係の存否
- 因果関係は条件関係があることを前提に、当該行為の持つ危険が結果に現実化したかにより判断します。本問のように、直接の死因が第2行為から生じている場合には、当てはめにおいては、第2行為(介在事情)が結果へ与えた寄与度を必ず認定しましょう。そして、第1行為が第2行為を誘発しており、かつ、第2行為の異常性が低いことを示すことにより、溺死は第2行為単独で生じたものではなく、第1行為と相まって生じたものと評価できるので、第1行為の持つ危険が結果に現実化したと結論付けることが出来ます。
- 因果関係の錯誤
- 主観的に予想した因果経過と、客観的に発生した因果経過が異なる場合に問題となる因果関係の錯誤ですが、どのような因果経過を辿ろうとも、客観的に因果関係が存在すると認められた以上は、結局は首を絞めて殺すという構成要件を認識しているのですから、因果関係の錯誤によって故意は阻却されません。したがって、簡潔に論じれば足ります。
- 因果関係の存否
- 第1行為について第1行為(実行行為)と溺死(結果)との間には、第2行為が介在しているため、因果関係が認められるかが問題となります。また主観的にも溺死するとは思っていないため、因果関係の錯誤も問題になります。
- 第2行為について
- 溺死という結果を直接引き起こしたのは第2行為ですから、第2行為の罪責もきちんと検討するべきです。
- 客観的に生きていたVを海に投げ入れて(実行行為)溺死(結果・因果関係)させていますから、殺人罪の客観的構成要件を充足します。
- ところが甲の主観ではVは死んでいると思っているのですから、殺人罪の故意はなく、死体遺棄罪の故意しかありません。そうすると、軽い罪の故意で重い罪を実現したことになりますが、これは38条2項により重い罪は成立しないと解釈されますので、殺人罪は成立しないことになります。
- では軽い罪である死体遺棄罪は成立するでしょうか。上記の通り、甲は死体遺棄罪の故意はあるので、あとは客観的に死体遺棄罪の客観的犯罪事実があればよいことになりますが、甲が実現したのは殺人罪です。そこで、客観的に存在する殺人罪の構成要件の中に死体遺棄罪の構成要件が含まれていれば(両構成要件に重なり合いがあれば)、死体遺棄罪の客観的犯罪事実があると評価できることになり、死体遺棄罪の成立を認めることができそうです。
- そこで両構成要件に重なり合いがあるかを、①保護法益に共通性があるか②行為態様に共通性があるかの2点から検討しますが、殺人罪の保護法益は人の生命であるのに対し、死体遺棄罪のそれは死者に対する宗教的感情ですから、①保護法益に共通性はありません。よって、構成要件の重なり合いがない以上、死体遺棄罪の故意に対応する犯罪事実がないので、故意犯は成立しないこととなります。
- 故意犯は成立しないとしても、過失犯は成立する可能性がありますので、検討漏れのないようにしましょう。
- 溺死という結果を直接引き起こしたのは第2行為ですから、第2行為の罪責もきちんと検討するべきです。
遅すぎた構成要件の実現は、予備試験ではH23とH31とR5の3回問われています。頻出論点ですから、しっかり学習しておきましょう。
参考文献

著者|DAI
社会保険労務士として働きながら令和4年予備試験、令和5年司法試験に合格。基本を徹底する丁寧な添削スタイルで着実に論文力を引き上げます。