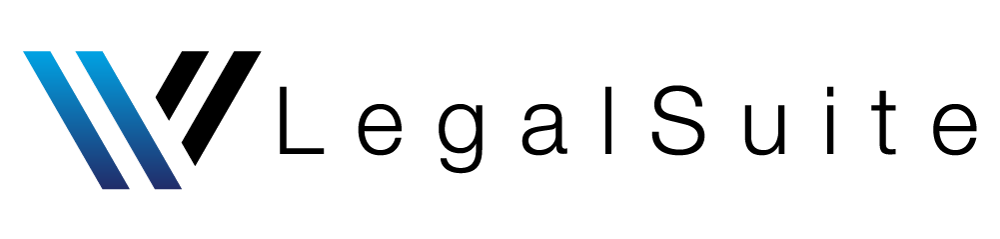【予備試験】令和5年刑法【答案例と解答のポイント】

出題の趣旨
〔設問1〕は、甲がXと山中にある無人の小屋で過ごしていた際、甲が同小屋から出て離れている間に熟睡しているXが目を覚まして同小屋から逃げないようにするため、同小屋の出入口扉を外側からロープで縛った行為に監禁罪が成立するという主張の当否について、具体的な事実関係を踏まえつつ、反対の立場からの主張にも言及して論述することを求めるものである。【事例1】では、Xは、熟睡しているため上記小屋から外に出る意思がなく、上記出入口扉をロープで縛られたことにも気付かず熟睡し続け、目覚める前にロープが解かれたことから、甲の行為は、Xの現実の移動の意思に影響を及ぼしていない。このような場合に監禁罪が成立するという主張の当否について、監禁罪の保護法益である移動の自由の意義に関して、反対する立場からの帰結やその問題点等にも留意しつつ論じなければならない。その際には、本件の具体的事実が保護法益論とどのように関連するのかを意識しながら論じる必要がある。
https://www.moj.go.jp/content/001411617.pdf
〔設問2〕は、甲が、⑴眠っていたXが所持していた携帯電話機を自分のリュックサックに入れ、⑵Xを殺害するため、眠っていたXの首を両手で強く絞め付け(以下「第1行為」という。)、Xが死亡したものと思い込んでいたところ、Xが所持していた財布内から現金3万円を抜き取って自分のポケットに入れ、さらに、⑶Xが死亡したものと思い込んだまま、実際には生きていたXを崖下に落とし(以下「第2行為」という。)、死亡させたことを内容とする事例について、甲の罪責に関する論述を求めるものである。
⑴では、甲は、Xの携帯電話機を離れた場所に捨てておけば、同携帯電話機のGPS機能によって発信される位置情報をXの親族等が取得したとしても、Xの死体発見を困難にできるなどという目的で、同携帯電話機を自己の占有下に移している。これは犯跡隠蔽の意図である一方で、同携帯電話機のGPS機能を利用する意図も含まれる点を踏まえ、甲に不法領得の意思を認めるか否かについて利用処分意思の内容を具体的に明らかにしつつ検討する必要がある。その上で窃盗罪あるいは器物損壊罪の成否を論じることになろう。
⑵では、甲が現金を抜き取ってポケットに入れた行為は窃盗罪の客観的構成要件を充足するが、Xが死亡していると誤信していることから、甲に窃盗罪の故意が認められるかについて、死者の占有を認めるか否かとの関係を明らかにしつつ検討する必要がある。
また、⑵の殺意をもって行われた第1行為から死亡結果が発生せず、⑶の殺意なく行われた第2行為によって死亡結果が発生した場合(いわゆる遅すぎた構成要件の実現)の殺人既遂罪の成否に関し、問責対象となる行為を特定して各行為の擬律判断(第1行為と死亡結果との因果関係及び因果関係の錯誤並びに第2行為の処理等)を検討する必要がある。
いずれについても、刑法の基本的な概念に関する正確な理解を前提に、事実関係を的確に分析し、それを法的に構成する能力や、具体的な事実を法的に分析する能力が問われている。
答案例
第1 設問1
監禁罪(刑法(以下略)220条後段)は成立するか。
1 熟睡している者が「人」にあたるか問題となる。
⑴ 本罪の保護法益は、人の場所的移動の自由である。ここでいう自由を、現実に移動しようと欲したときに移動できる自由を指すと考える見解がある。この見解によれば、「人」といえるためには、被監禁者が監禁されていることを認識した状態で、移動したいと欲している必要がある。本件で、Xは午後5時5分頃から午後6時頃まで熟睡していたのであるから、監禁されていることを認識しておらず、また移動したいとも欲していない。よって、この見解によれば、Xは「人」にあたらず本罪は成立しない。
もっとも、この見解によると、相手方を殴って気絶させてから閉じ込めた場合、一律に監禁罪が成立しないこととなり、妥当性に欠ける。
⑵ そこで、人の場所的移動の自由とは、移動しようと思えば移動できる自由を指す見解に立つ。この見解によれば、「人」といえるためには、移動する可能性さえ認められればよいから、監禁されていることを認識する必要もなく、また、移動したいと欲する必要もないと考える。
本件で、Xは上記の通り熟睡により監禁されていることを認識しておらず、また移動したいとも欲していないが、物音等で起きる可能性がある以上移動する可能性もあるから、移動しようと思えば移動できる自由を侵害されているので、「人」にあたる。
2 「監禁」とは一定の区域から脱出できないようにして場所的移動を不可能又は困難にすることをいうと考える。本件において、小屋は木造平屋建てで窓がないから、外への出口は扉しか方法がない。ところがその扉は、甲が外側からロープできつく縛り、内側からは開けられないようにしていたのであるから、本件小屋から脱出できないようにして場所的移動を不可能にしているといえ、「監禁」にあたる。
3 この監禁についてXの同意はないから「不法に」にあたる。
4 甲はこれらの事実を認識・認容しているから故意(38条1項本文)がある。
以上から、甲に監禁罪が成立する。
第2 設問2
1 Xの携帯電話を取り出し、甲のリュックサックに入れた行為について窃盗罪(235条)は成立するか。
⑴ 本件携帯電話はXの占有するXの所有物であるから「他人の財物」にあたる。
⑵ 甲は、Xの意思に反して、本件携帯電話をXの上着のポケットから取り出して自己の占有下に移しているから、「窃取」にあたる。そして、本件携帯電話の大きさからして、リュックサックに入れれば発見は困難になるから「窃取した」にあたる。
⑶ 甲はこれらの事実を認識・認容しているから故意がある。
⑷ 不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として(権利者排除意思)、その経済的用法に従い利用処分する意思(利用処分意思)をいうと考える。これらが必要なのは、権利者排除意思は占有移転段階で不可罰的使用窃盗と区別するため、利用処分意思は占有移転段階で毀棄・隠匿罪と区別するため、行為者の主観面を考慮せざるを得ないからである。
本件で、甲は本件携帯電話をリュックサックに入れた約3時間50分後に、崖から約6キロメートル離れた場所で本件携帯電話を捨てている。このことから、占有移転段階で返還の意思がないといえるから、権利者排除意思は認められる。もっとも、携帯電話のGPS機能により発信される位置情報を使い、死体発見を困難にするという効用は、携帯電話を盗むことにより間接的に得られる反射的な利益に過ぎず、携帯電話という財物から得られる直接的な効用ではない。よって、目的物の持つ効用を直接に享受する意思がないので、経済的利用処分意思はなく、不法領得の意思は認められない。
以上から、窃盗罪は成立しない。
2 では、同行為に器物損壊罪(261条)は成立するか。
⑴ 本件携帯電話は「他人の物」であり、甲はそれを隠匿してその効用を害しているから「損壊」している。
⑵ 甲はこれらの事実を認識・認容しているから故意がある。
以上から、①器物損壊罪(261条)が成立する。
3 Xを殺害した行為に殺人罪(199条)は成立するか。
⑴ 「殺」すとは死の結果発生の危険性ある行為をいうと考える。本件で、甲はXの首を片手ではなく両手で、しかも強く締め付けており、さらにXがぐったりするまで締め続けている。これは死の結果発生の危険性ある行為をしており、「殺」すにあたる。そして、Vの死亡という結果が発生している。
⑵ もっともXの死因は頭部外傷であるから因果関係があるか。因果関係は条件関係が認められることを前提に、行為の持つ危険が結果へと現実化したといえることが必要であると考える。本件で、甲が首を締めなければXは死亡しなかったから条件関係はある。そして死因が頭部外傷である以上介在事情の寄与度は大きい。もっとも、この頭部外傷は証拠隠滅のために行われた結果なのであるから、甲の絞首行為に誘発されている。しかも証拠隠滅のために死体を隠すことはままあるから異常性は低い。よって、行為の持つ危険が結果へと現実化したといえるから、因果関係がある。
⑶ 甲はXがぐったりするまで首を絞めているから、絞首行為の危険性を認識しているし、𠮟責による恨みを晴らすという動機もあるので、認容もある。よって故意が認められる。
⑷ そして頭部外傷という因果経過は認識していないが窒息死という因果経過を認識している以上、反対動機の形成は可能であるから故意は阻却されない。
以上から②殺人罪(199条)が成立する。
4 Xを崖下に落下させた行為に過失致死罪(210条)は成立するか。
⑴ 甲は生きているXを崖下に落下させて殺しているから、客観的には殺人罪を実現しているが主観的には死体遺棄罪(190条)の故意しかないため、抽象的事実の錯誤の問題となる。
「重い罪」で「処断…できない」(38条2項)とは、責任主義の観点から重い罪は成立しないという意味であると考える。よって殺人罪は成立しない。
⑵ 本件では軽い罪の死体遺棄罪の故意はあるから、殺人罪の構成要件の中に死体遺棄罪の構成要件が含まれているか問題となる。その際には、保護法益に共通性があるか否かにより判断する。本件で、殺人罪の保護法益は人の生命である一方、死体遺棄罪のそれは死者に対する宗教的感情であるから共通性がない。よって、殺人罪の構成要件の中に死体遺棄罪の構成要件が含まれていない。以上から故意犯は成立しない。
⑶ もっとも、より注意をすればXが生きていたことに気付けたので甲に過失が認められ、③過失致死罪(210条)が成立する。
5 3万円を奪った行為に窃盗罪(235条)は成立するか。
⑴ 3万円は、Xの占有するXの所有物であるから「他人の財物」にあたる。
⑵ 甲はXの意思に反して、本件3万円を財布から抜き取っており自己の占有下に移しているから、「窃取」にあたる。そして、ズボンのポケットに入れれば発見は困難になるから「窃取した」にあたる。
⑶ 甲は3万円を奪った時点でXが死亡したと誤信しているため、窃盗罪の故意が認められるか問題となる。
ア 故意とは犯罪事実の認識・認容であるから、行為者の認識・認容した事実を前提にして犯罪が成立するのであれば、故意が認められることになるといえる。そして死者には占有がないことが原則であるが、被害者を殺害した者との関係で、殺害行為と窃盗行為が時間的場所的に近接した範囲内にあるならば、両行為を一体的に捉え、生前の占有を侵害したものと言えると考える。
イ 本件では、午後6時20分頃に、甲がXを殺したと思っている。そして窃盗行為は午後6時25分頃に行われているから、時間的に近接している。さらに場所も同じ場所で行われているから、場所的にも近接している。よって、殺害行為と窃盗行為は一体的に捉えることが出来るので生前の占有を侵害したこととなる。そうすると、甲の認識では「他人の財物を窃取した」という認識であるから、窃盗罪の故意が認められる。
⑷ 不法領得の意思も明らかに認められる。
以上から、④窃盗罪(235条)が成立する。
6 罪数
甲には、①器物損壊罪(261条)、②殺人罪(199条)、③過失致死罪(210条)、④窃盗罪(235条)が成立する。死の二重評価を避けるために③は②に吸収される。それと①④は併合罪(45条前段)となる。
以上
解答のポイント
監禁罪(220条後段)
- 保護法益は場所的移動の自由です。
- 成立要件は、以下の通りです。
- 人を(客体)
- 監禁した(実行行為)
- 不法に(違法性阻却事由の不存在)
- 客体のポイント
- 保護法益である場所的移動の自由をどのように考えるかにより、「人」に当たるか否かが変わります。
- 場所的移動の自由を、移動したいと欲する意思さえ保護すれば足りるとして、現実に移動しようと欲したときに移動できる自由(現実的自由説)と考える見解があります。このように考えると、現実に移動したいのにできない場合には「人」にあたりますが、現実に移動しようと思っていない以上は、「人」にあたらないと考えることになります。よって、熟睡している者は、移動しようと思っていないため、「人」に当たらず監禁罪は成立しないこととなります。
- 他方、場所的移動の自由を、移動するかしないかの選択肢が存在することに意義があるとして、移動する可能性さえ認められればよいから、移動しようと思えば移動できる自由(可能的自由説)と考える見解があります。この見解によれば、熟睡している者でも将来的に起きて移動する可能性がある以上は、「人」に当たることとなります。
- 保護法益である場所的移動の自由をどのように考えるかにより、「人」に当たるか否かが変わります。
- 実行行為のポイント
- 「監禁」とは、一定の区域から脱出できないようにして場所的移動を不可能又は困難にすることをいいます。定義はきっちり暗記しましょう。なお、同条前段の「逮捕」とは、直接的な強制作用を加えて場所的移動の自由を奪うことを言います。こちらも記憶しておきましょう。
窃盗罪(235条)
- 保護法益は所有権と占有です。
- 成立要件は、以下の通りです。
- 他人の財物を(客体)
- 窃取(実行行為)
- した(結果)
- 不法領得の意思
- 客体のポイント
- 「他人の」という条文の言葉遣いからして、財物は他人の所有物であることを前提としていると考えられています。また、窃取するためには占有されている状態が必要ですから(占有されていないなら占有離脱物横領罪となる)、まとめると「他人の財物」とは、他人が占有する他人の所有物を指します。この定義は答案に示せるよう暗記しましょう。
- なお、”占有とは財物に対する事実的支配をいい、占有の事実と占有の意思を総合し、社会通念に従い判断する”という規範があります。これは、占有の存否が問題になる場合に用いる規範です。そして、上記の通り占有しているか否かは客体の問題です。「窃取」という実行行為で論じるのではなく、「他人の財物」という客体を検討する際に論じるようにしましょう。
- 「他人の」という条文の言葉遣いからして、財物は他人の所有物であることを前提としていると考えられています。また、窃取するためには占有されている状態が必要ですから(占有されていないなら占有離脱物横領罪となる)、まとめると「他人の財物」とは、他人が占有する他人の所有物を指します。この定義は答案に示せるよう暗記しましょう。
- 実行行為のポイント
- 「窃取」とは、占有者の意思に反して、占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移転することをいいます。必ず暗記しましょう。
- 結果のポイント
- 「窃取した」すなわち既遂に至ったといえるためには、占有を取得したことが必要です。本問の両行為はあっさり認定できる事例ですが、既遂時期を悩ませる問題では厚く論じるようにしましょう。占有を取得したことの裏返しは、被害者が占有を喪失したときですから、財物の大小、場所、搬出の容易性などから検討することを押さえておきましょう。
- 故意のポイント
- 故意は窃盗罪に限らず要求される主観的要件ですから、あえて冒頭の成立要件には掲げていませんが、本問では死者の占有という論点を故意に位置づけて論じさせる問題でした。以下で死者の占有について整理しましょう。
- 通常、死者の占有が問題になるのは、客観的に死んでいる人間の有していた財物を窃取した場合に議論されます。すなわち、死者には占有の意思がなく、占有そのものが認められないため、他人の占有する他人の所有物(「他人の財物」)という客体にあたらないことになります。そうすると、誰も占有していない財物を取得しただけなので、原則として窃盗罪が成立せず、占有離脱物横領罪(254条)が成立することになります。しかしながら、自らの殺害行為により被害者の占有を失わせておきながら占有離脱物横領罪しか成立しないのはあまりにも不合理です。そこで、殺害行為と窃取行為が時間的場所的に近接した範囲内にあれば、両行為の一体性が肯定でき、その結果、生前の占有を侵害したと評価して窃盗罪の成立を認めていくことになります(最判昭41.4.8)。
- これに対し、本問ではXは客観的には生きています。死んでないということは、客観面では死者の占有は全く問題になりませんので、客体と実行行為を通常通りに認定すれば足ります。問題なのは、甲の主観面ではXが死んだものと思い込んでいる点です。すなわち、甲の主観面では、死者から財物を奪っただけなので、窃盗罪の故意があるかを検討する必要があります。
- 故意というのは、犯罪事実の認識・認容ですから、行為者の認識において、生前の占有を侵害したといえるならば、窃盗罪の故意が認められることとなります。類題が出題されたH29司法試験の出題趣旨も参考になります。
甲と乙がAから財布を奪った時点で,甲と乙はAが死亡したものと認識していたため,窃盗罪の故意に関してAの占有を侵害する認識が認められるかが問題となる。死者の占有について,判例の立場(最判昭和41年4月8日刑集20巻4号207頁等)による場合には,「被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して財物を奪取した」と認められるかを検討しなければならない。そして,Aの占有を侵害する認識を肯定する場合,客観的に窃盗罪の構成要件に該当するのみならず,窃盗罪の故意が認められる(H29司法試験刑事系科目第1問出題趣旨抜粋)。
https://www.moj.go.jp/content/001236007.pdf
- 不法領得の意思のポイント
- 不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物として(権利者排除意思)その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思(利用処分意思)をいいます。書かれざる構成要件要素として必要になりますので、定義は暗記しましょう。
- 権利者排除意思について整理しましょう。「他人の財物を窃取した」時点で窃盗罪は既遂となります。ところがその財物がすぐに被害者の手元に戻ってきた場合には、保護法益である所有権や占有への侵害が軽微であるため、不可罰(使用窃盗)と評価されます。他方、財物が盗まれたまま戻ってこなかったら、所有権や占有への侵害が認められますので、窃盗罪が成立します。ところが、すぐに手元に戻ってきたか否かというのは、既遂に達した後の事情ですから、既遂以後の事情を犯罪の成否の検討に用いることはできません。そこで、占有移転時点において、行為者にはすぐに返すつもりがあったのか否かという行為者の主観面を考慮せざるを得ません。以上を前提にして、権利者排除意思とは、不可罰的使用窃盗と窃盗罪を区別するために要求されると理解されています。
- 次に利用処分意思について整理しましょう。例えば、他人の財物をその場で破壊すれば器物損壊罪が成立しますが、他人の財物を窃取してから別の場所で財物を破壊すれば、すでに占有移転がある以上、客観的に見れば窃盗罪が成立します。もっとも、最終的には両者ともに財物が破壊されており、その場で壊すか移動してから壊すかに大差はないため、両者はいずれも器物損壊罪で良いのではないかとの疑問が生じます。そもそも、器物損壊罪は財物を破壊し回復不可能な状態へと変化させてしまうにも関わらず、窃盗罪の法定刑の方が器物損壊罪のそれより重いのは、その財物を利用してやろうという動機・目的の方が強い法的非難に値すると評価されているからです。そうすると、占有移転段階においてその財物を利用してやろうという意思があったか否かという行為者の主観面を考慮せざるを得ません。以上を前提にして、利用処分意思とは、毀棄・隠匿罪と窃盗罪を区別するために要求されると理解されています。そして、利用処分意思の具体的な中身としては「財物から直接的に何らかの効用を享受する意思」が必要であると整理されています。
- さて、本問における携帯電話のGPS機能は、財物から生ずる直接的な効用と言えるでしょうか。たしかに、誤った位置情報によってXの死体の発見には至っていないのですから、占有移転段階における甲の目的は果たされていると言えるでしょう。しかし、携帯電話本来の効用というのは通話機能であり、GPS機能は副次的・間接的な効用であると思われます。甲は通話機能を利用してやろうという意図ではなく、GPS機能を使って死体の発見を困難にしてやろうという意図だったので、そのように考えるのが自然と思われます。もっとも、本問の出題趣旨によれば、窃盗罪の成立もあり得ることが示されています。問題文4には5行にも渡って利用処分意思に関する事実が豊富に存在していますから、利用処分意思に関する規範を答案に示し、充実した当てはめができれば、結論はいずれでも構わないと思われます。
- ちなみに、本問類似の事案において、裁判例(松山地判平成19.7.19)では、利用処分意思がないと判断されて不法領得の意思が否定されています。また、不法領得の意思の存否が問われたH27司法試験の出題趣旨も参考になります。
不法領得の意思について,その概念を述べるだけでなく,その内容にも踏み込んで論述し,これに丙の意思を当てはめて,丙に不法領得の意思を認めることができるのかを論ずることが肝要である。本件のようないわゆる刑務所志願の事案については,下級審の裁判例でも結論が分かれているところであり,いずれの結論を採るにしても,自らが提示した不法領得の意思の概念を踏まえて事実を当てはめて結論することが求められている。仮に,丙について不法領得の意思を否定した場合には,毀棄罪,具体的には器物損壊罪の成否を論ずることが必要である。
https://www.moj.go.jp/content/001166241.pdf
遅すぎた構成要件の実現
第1行為で結果が生じたと誤信して、犯行隠蔽のために第2行為に及んだら第2行為で結果を実現してしまった場合、両行為は別々に検討する必要があります。なぜなら、第1行為は殺害目的で行われ、第2行為は死体隠蔽のために行われているので、意思の連続性がないため両行為を一体的に捉えることはできないからです。
- 第1行為について
- 第1行為について第1行為(実行行為)と溺死(結果)との間には、第2行為が介在しているため、因果関係が認められるかが問題となります。また主観的にも溺死するとは思っていないため、因果関係の錯誤も問題になります。
- 因果関係の存否
- 因果関係は条件関係があることを前提に、当該行為の持つ危険が結果に現実化したかにより判断します。本問のように、直接の死因が第2行為から生じている場合には、当てはめにおいては、第2行為(介在事情)が結果へ与えた寄与度を必ず認定しましょう。そして、第1行為が第2行為を誘発しており、かつ、第2行為の異常性が低いことを示すことにより、溺死は第2行為単独で生じたものではなく、第1行為と相まって生じたものと評価できるので、第1行為の持つ危険が結果に現実化したと結論付けることが出来ます。
- 因果関係の錯誤
- 主観的に予想した因果経過と、客観的に発生した因果経過が異なる場合に問題となる因果関係の錯誤ですが、どのような因果経過を辿ろうとも、客観的に因果関係が存在すると認められた以上は、結局は首を絞めて殺すという構成要件を認識しているのですから、因果関係の錯誤によって故意は阻却されません。したがって、簡潔に論じれば足ります。
- 因果関係の存否
- 第1行為について第1行為(実行行為)と溺死(結果)との間には、第2行為が介在しているため、因果関係が認められるかが問題となります。また主観的にも溺死するとは思っていないため、因果関係の錯誤も問題になります。
- 第2行為について
- 溺死という結果を直接引き起こしたのは第2行為ですから、第2行為の罪責もきちんと検討するべきです。
- 客観的に生きていたVを海に投げ入れて(実行行為)溺死(結果・因果関係)させていますから、殺人罪の客観的構成要件を充足します。
- ところが甲の主観ではVは死んでいると思っているのですから、殺人罪の故意はなく、死体遺棄罪の故意しかありません。そうすると、軽い罪の故意で重い罪を実現したことになりますが、これは38条2項により重い罪は成立しないと解釈されますので、殺人罪は成立しないことになります。
- では軽い罪である死体遺棄罪は成立するでしょうか。上記の通り、甲は死体遺棄罪の故意はあるので、あとは客観的に死体遺棄罪の客観的犯罪事実があればよいことになりますが、甲が実現したのは殺人罪です。そこで、客観的に存在する殺人罪の構成要件の中に死体遺棄罪の構成要件が含まれていれば(両構成要件に重なり合いがあれば)、死体遺棄罪の客観的犯罪事実があると評価できることになり、死体遺棄罪の成立を認めることができそうです。
- そこで両構成要件に重なり合いがあるかを、①保護法益に共通性があるか②行為態様に共通性があるかの2点から検討しますが、殺人罪の保護法益は人の生命であるのに対し、死体遺棄罪のそれは死者に対する宗教的感情ですから、①保護法益に共通性はありません。よって、構成要件の重なり合いがない以上、死体遺棄罪の故意に対応する犯罪事実がないので、故意犯は成立しないこととなります。
- 故意犯は成立しないとしても、過失犯は成立する可能性がありますので、検討漏れのないようにしましょう。
- 溺死という結果を直接引き起こしたのは第2行為ですから、第2行為の罪責もきちんと検討するべきです。
本問は司法試験のように見解対立問題が出題された点に特徴があります。また、窃盗罪を真正面から問うた問題でもあります。窃盗罪は財産犯の基本となりますので、しっかりマスターしておきましょう。総論編から出題されている遅すぎた構成要件の実現は、予備試験ではH23とH31とR5の3回問われています。頻出論点ですから、しっかり学習しておきましょう。
参考文献

著者|DAI
社会保険労務士として働きながら令和4年予備試験、令和5年司法試験に合格。基本を徹底する丁寧な添削スタイルで着実に論文力を引き上げます。